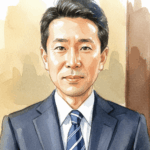飲食店の居抜き譲渡の場合の所得区分
長年営んでこられたお店を売却されたとのこと、税金のことがご心配になるのは当然です。
専門用語が多くて難しく感じますよね。
大丈夫です、一つひとつ分かりやすくご説明します。
お店を丸ごと売ることを「居抜き売却」と言いますが、税金の計算をするときは、「お店一式をドン!」と一つの塊で考えるのではなく、中身をパーツごとに分解して考えるのがポイントです。
ちょうど、一台の車を売るのではなく、「エンジン」「タイヤ」「カーナビ」と値段を分けて考えるイメージですね。
まず、本当の「売上」はいくら?
今回、買主さんから3,000万円を受け取られました。
しかし、あなたが大家さんに預けていた保証金500万円は、買主さんが引き継いでくれましたね。
これは、あなたが返してもらうはずだった500万円を、買主さんが代わりに受け取る権利を得た、ということです。
ですので、税金の計算を始めるにあたって、今回の取引での実質的な売上は、3,000万円からこの保証金500万円を差し引いた2,500万円と考えます。
利益の種類は「2つ」に分けて考えます
次に、この2,500万円の売上を、売ったモノの性質によって「2種類の利益」に仕分けしていきます。
事業所得(いつもの商売と同じ利益)
こちらは、普段の商売で得られる利益と同じ扱いのものです。
- 食材や飲み物などの在庫
- 10万円未満で買った食器や調理器具などのこまごました備品
などがこれにあたります。いわば「日々の商売の延長線上にある利益」ですね。
譲渡所得(不動産などを売ったときと同じ、臨時の利益)
こちらは、土地や建物を売ったときと同じように、特別な臨時収入として扱われる利益です。
お店の価値の大部分がこちらに含まれます。
- お店の内装やカウンターなどの造作
- 冷蔵庫や厨房機器など、高価な設備(目安として10万円以上で買ったもの)
- その場所でお店を続けられる権利(専門用語で「借家権」といいます)
などが、この「譲渡所得」として計算されます。
「譲渡所得」の儲け(利益)の計算方法
「譲渡所得」の利益は、単純な売上金額ではありません。
「売上」から「かかった経費」を差し引いて計算します。
譲渡所得の利益 = 売上 - (取得費 + 譲渡費用)
- 取得費とは?
あなたがこのお店を手に入れたときにかかった元手のことです。今回のケースでは、最初に支払った1,500万円から保証金500万円を除いた1,000万円が元になります。
ただし、お店の設備は年々価値が下がっていきますよね(これを減価償却といいます)。その価値が下がった分を差し引いた、現時点での資産価値が「取得費」となります。 - 譲渡費用とは?
今回、お店を売るために直接かかった費用のことです。
例えば、大家さんに支払った名義書換料50万円などがこれにあたります。
「のれん代(営業権)」について
「のれん代」や「営業権」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
これは、お店のブランド力や長年のお得意様といった「目に見えない価値」のことです。
しかし、飲食店の場合は、経営者が変わるとお店の味や雰囲気も変わってしまうのが一般的です。
そのため、税金の計算上は「営業権はないもの」として考えることがほとんどです。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。お店を売ったときの税金は、
- 保証金を差し引いて、本当の売上を出す
- 売ったものを「日々の商売の利益」と「臨時の利益」に分ける
- 「臨時の利益」は、元手や手数料を差し引いて計算する
という流れになります。
このように、中身を細かく分けて計算する必要があり、少し複雑に感じられるかもしれません。