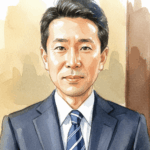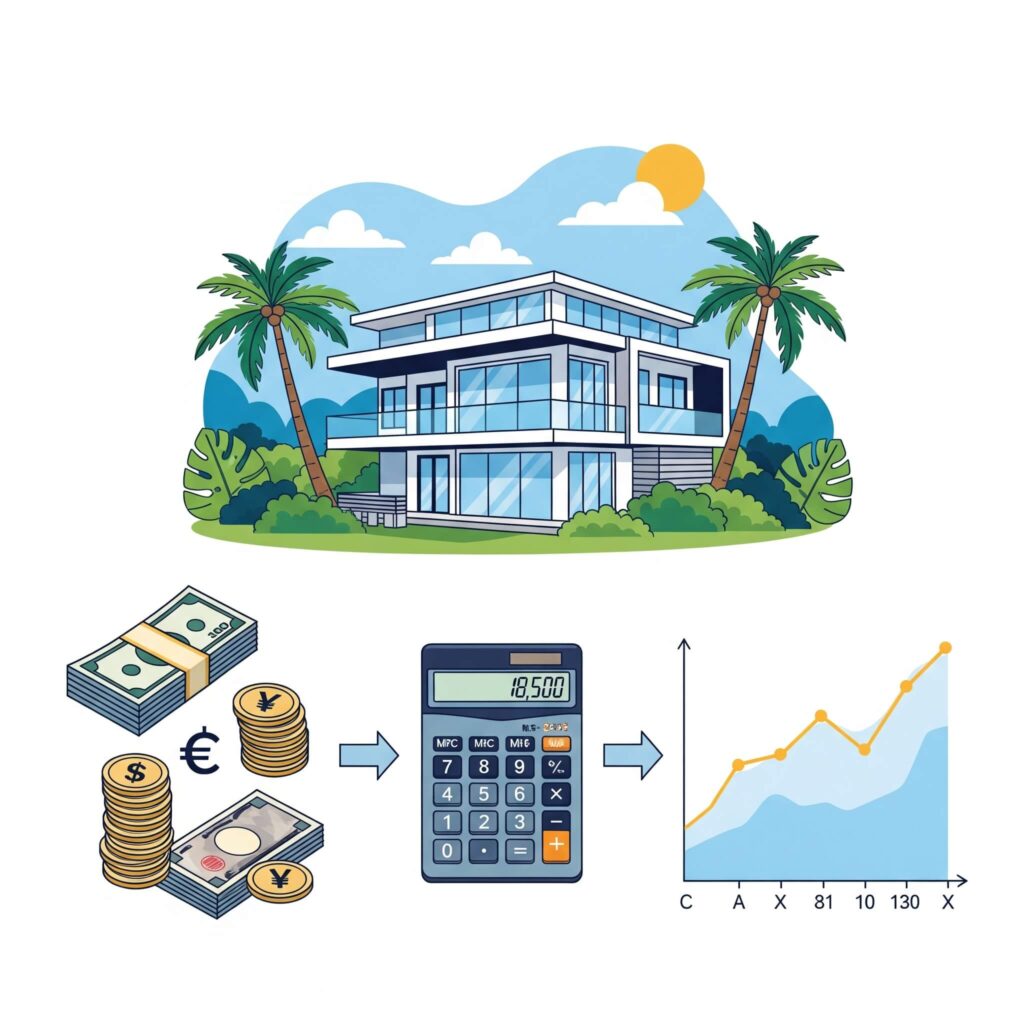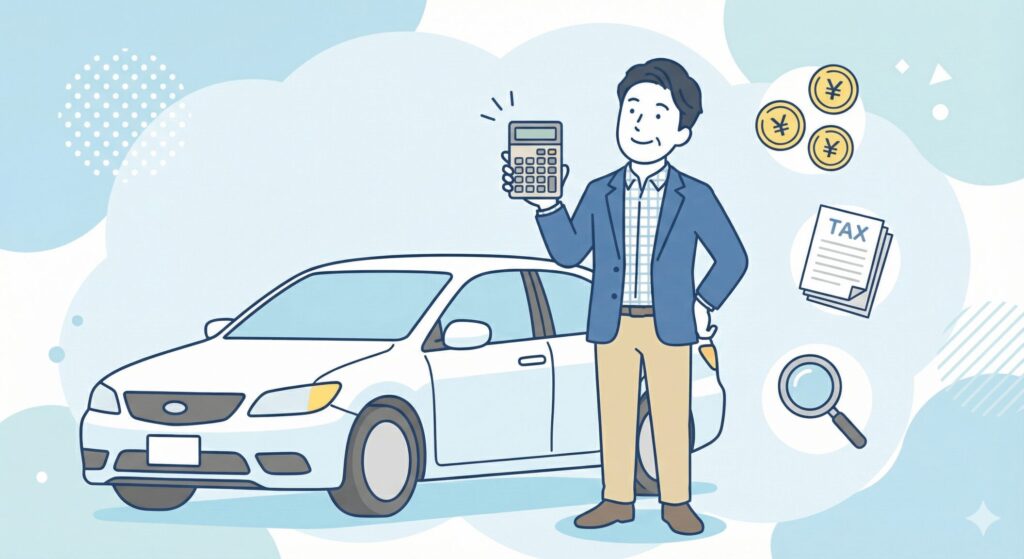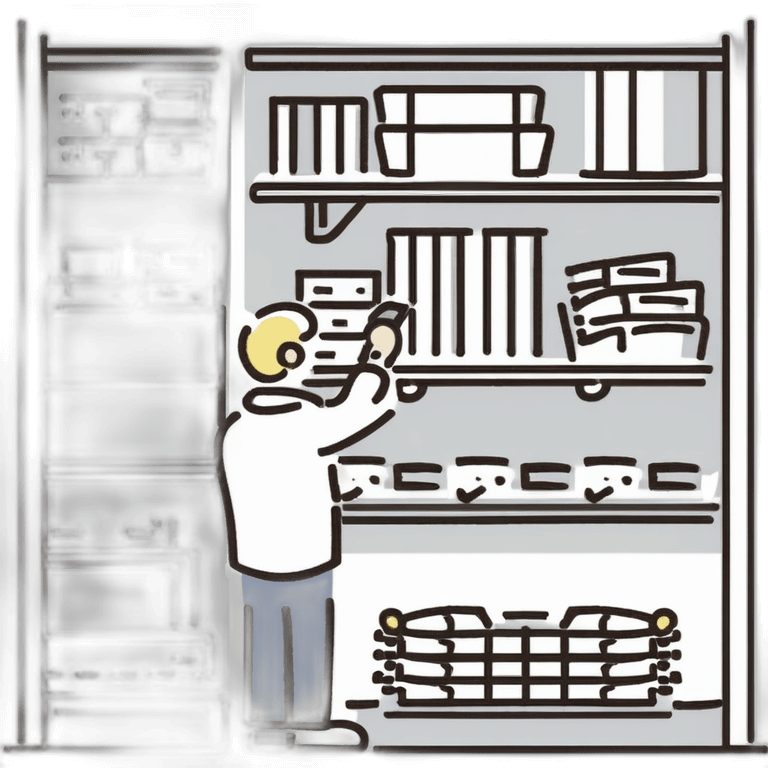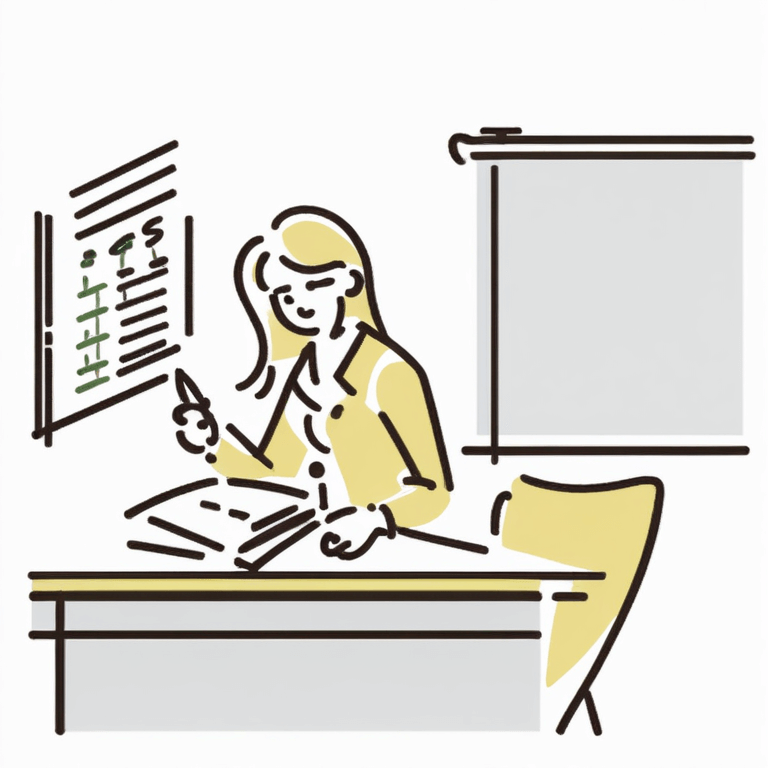
お店の権利を売ったり買ったりした時の税金の話
お店の権利を譲ったり、譲り受けたり…なんだか難しそうに聞こえますよね。
専門用語が多くて戸惑うのも無理はありません。
ここでは、お店の「お得意様と取引できる権利」を売ったり買ったりした場合の税金のルールを、ラーメン屋さんに例えて分かりやすく解説しますね。
お店を譲渡した側(売る人)の税金
お店を売るとひとくちに言っても、何を売ったかによって税金の計算方法が変わります。
大きく3つに分けて考えてみましょう。
「のれん(営業権)」を売った利益
これは、長年かけて築き上げたお店の信用やブランド力、お得意様との関係を売ったときの利益です。目には見えない価値ですね。
ラーメン屋さんで言えば、秘伝のレシピや「あの店はうまい!」という評判のことです。
この利益は、その年の給料など他の所得と合算して、まとめて税金が計算されます。
「土地・建物」を売った利益
お店の建物や土地を売って出た利益は、とても金額が大きくなることが多いですよね。
そのため、他の所得とは混ぜずに、これだけで特別に税金が計算されます。
これを「分離課税」と言いますが、「特別なポケットに入れて別計算する」とイメージしてください。
「厨房機器や備品」を売った利益
お店で使っていた机や椅子、パソコン、ラーメンの茹で釜などの備品を売った利益は、「のれん」と同じように、他の所得と合算して税金が計算されます。
<例外>
ただし、一つ10万円もしないような少額な備品を売った利益は、「事業所得」という扱いになります。
これは、わざわざ「売却益」として難しく計算するのではなく、「今年の事業の儲けが少し増えた」というシンプルな扱いで良いですよ、というルールです。
お店を譲り受けた側(買う人)の税金
今度は、お店を買った人の立場です。
あなたが、評判のラーメン屋さんを買い取ったとします。
その際に支払った「のれん代(営業権)」は、どうなるのでしょうか?
これは、「目に見えない資産」を買ったと考えます。
そして、支払った「のれん代」は、5年間に分割して経費にすることができます。
例えば、のれん代として500万円支払った場合、毎年100万円ずつ(500万円÷5年)を事業の経費として計上できるのです。
経費が増えれば、その分、納める税金が少なくなります。
「大きな買い物をしたけれど、その価値は5年間続くから、費用も5年間に分けて計上しましょうね」という考え方です。
消費税はどうなるの?
お店を丸ごと売買するとき、消費税がかかるものとかからないものが混在しています。
スーパーで買い物かごに商品を入れるのを想像してください。
「土地」は消費税がかからない非課税商品ですが、「建物」や「厨房機器」、「のれん(営業権)」は消費税がかかる課税商品です。
そのため、売買の際には、それぞれの資産が課税対象かどうかを一つひとつ分けて、消費税を正しく計算する必要があります。