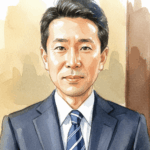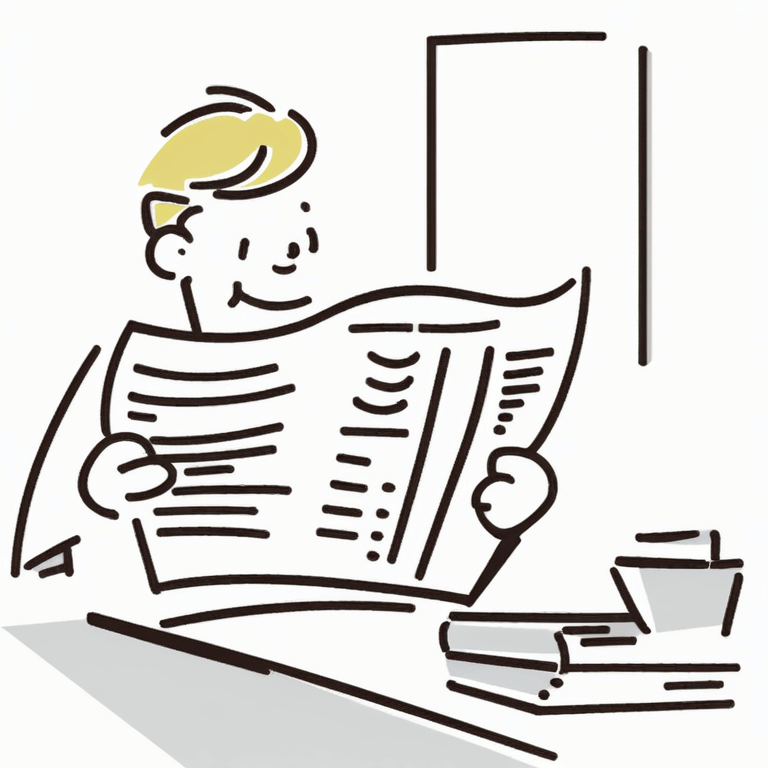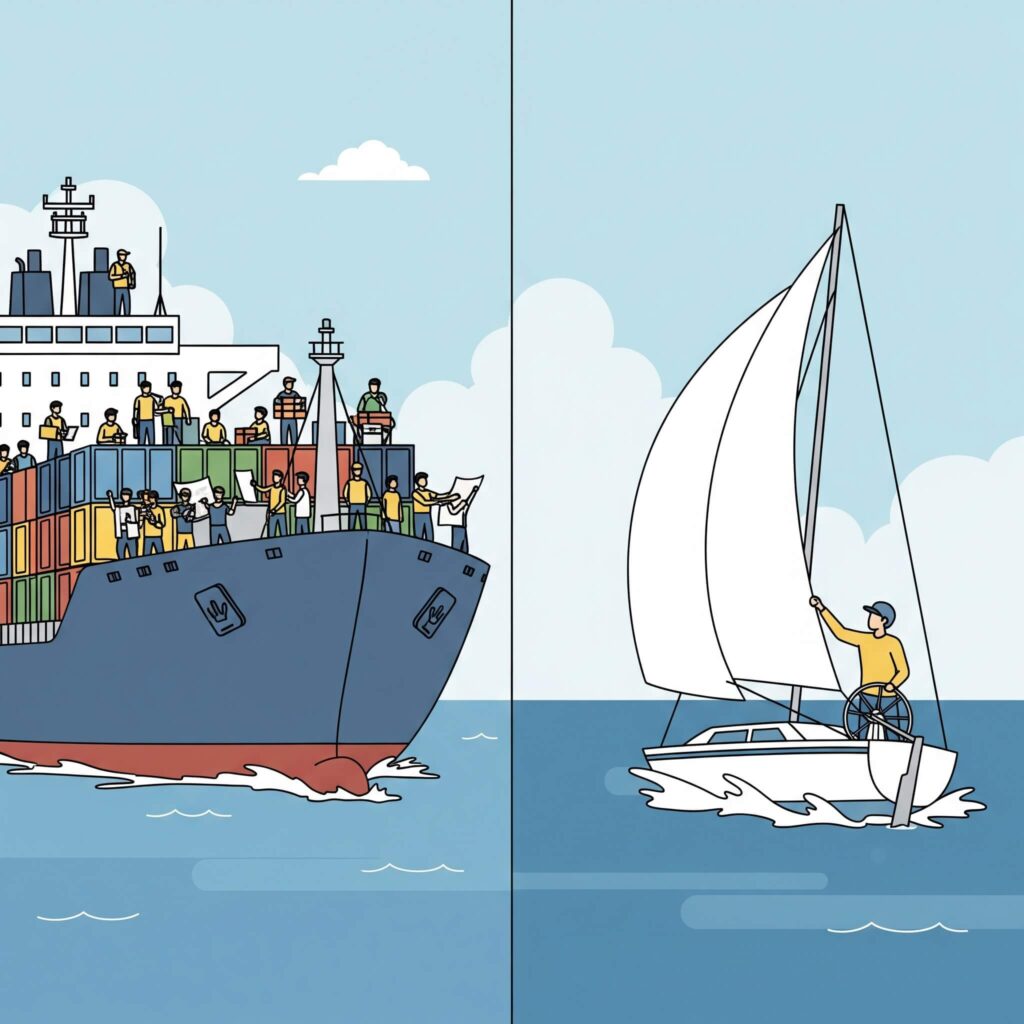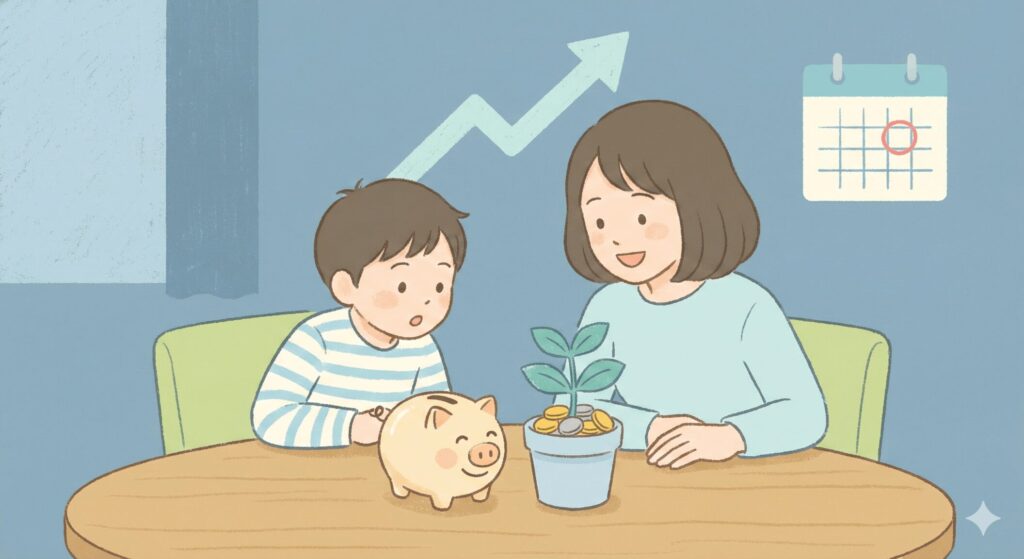不動産所得の総収入金額の収入すべき時期
Q1. 家賃収入は、いつ「売上」として数えるの?
A. 原則は「実際に入金された日」ではなく「契約で決めた支払日」です。
税金の計算では、実際にお金が手元に入ってきたかどうかに関わらず、収入を得る権利が確定した時点で売上として数える、というルールがあります。
これを大家さんのお仕事に当てはめてみましょう。
大家さんと入居者さんとの間では、「毎月末に家賃を支払う」という契約を結んでいますよね。
この契約で定められた「毎月末日」が来た時点で、「今月分の家賃収入を得る権利が確定した」と考えます。
たとえ入居者さんの都合で支払いが遅れていても、月末が来たら、帳簿には「今月分の家賃収入があった」と記録する必要があるのです。
【例え話:なじみのお店での「ツケ払い」】
なじみのお店で買い物をし、「支払いは月末にまとめて」とツケでお願いしたとします。お店側は、商品を渡した日に「売上」を記録しますよね。
実際にお金を受け取るのが月末だとしても、売上が立ったのは商品を渡した日です。
これと全く同じ考え方です。
大家さんにとっての「商品を渡した日」が、「お部屋を1ヶ月貸しした月の末日」にあたるわけです。
Q2. 裁判中で「供託」されている家賃はどうなるの?
A. これも同じく「契約で決めた支払日」に売上として数えます。
「供託」とは、大家さんが受け取ってくれないなどの理由で、入居者さんが法務局という国の機関に家賃を預ける制度です。
大家さんからすれば、まだ直接お金を受け取れていないので、収入ではないように感じられるかもしれません。
しかし、税金のルールでは、これも「契約上の支払日(毎月末)」に大家さんの収入として数えることになります。
【例え話:共通の金庫】
入居者さんは、大家さんに直接渡せない代わりに、「共通の金庫(法務局)」にきちんとお金を入れている状態です。
お金の保管場所が一時的に変わっているだけで、大家さんの収入であることに変わりはない、と考えてください。
もし裁判の結果、家賃の値上げが認められた場合は、少し扱いが変わります。
例えば、もともと月5万円で、6万円に値上げする裁判をしていたとします。
入居者さんは5万円を供託していました。
裁判で6万円の家賃が認められた場合、供託されていた5万円は毎月末の収入として計上し、差額の1万円については、裁判で値上げが正式に決まった日に、まとめて収入として計上することになります。
【補足】逆に、家賃を「値下げ」して返金した場合は?
ご質問とは逆のケースですが、景気の変動などで家賃を値下げし、過去に遡って差額を入居者さんに返金することになった場合のルールも簡単にご紹介します。
これは、大家さんのアパート経営が「事業的規模」かどうかで扱いが変わります。
大家さんのように30戸も所有されている場合は、一般的に「事業的規模」と判断されます。
- 事業的規模の場合(大家さんのケースはこちらに該当する可能性が高いです)
差額を返金した年に、その返金額をまるごと「必要経費」として計上できます。
お店で言えば、「返品があったので、その年の経費が増えた」というようなシンプルな処理で済みます。 - 事業的規模でない場合(例えば、アパートを1~2室だけ貸している場合など)
こちらは少し手続きが複雑になります。
過去の各年について、「本当の家賃収入はもっと少なかったです」と税務署に申告をやり直し(これを「更正の請求」といいます)、払いすぎていた税金を返してもらう手続きが必要になります。
いかがでしたでしょうか。
税金の計算は、実際のお金の動きと少しずれることがあるため、戸惑われるかもしれません。
まずは「収入を数えるタイミングは、契約で決めた支払日が基本!」と覚えていただければ大丈夫です。
もちろん、これは一般的なご説明ですので、個別の事情によって判断が異なる場合もあります。