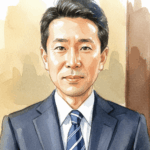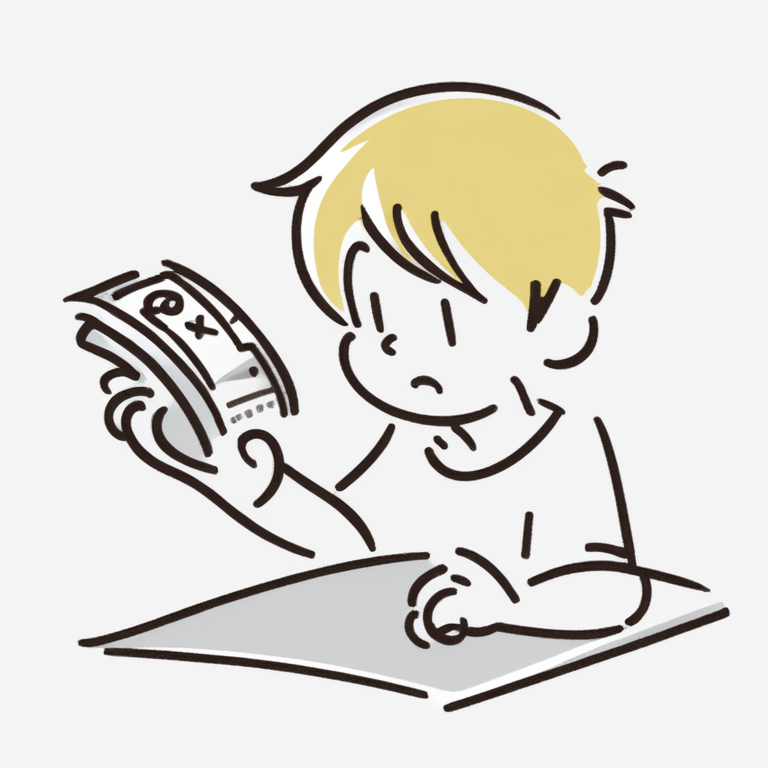職務発明の対価と源泉徴収
会社が従業員の「職務発明」に対して、社内規程に基づいてお金を支払うことがあります。
職務発明とは、仕事の中で生まれた発明のことです。
たとえば、次のような支払い方があります。
- 会社名義で特許として登録できた時点で、一定額を支払う(例:100万円)
- 特許登録後、販売実績(売上や利益など)に応じて、追加で支払う(例:初年度120万円)
2つ目の支払いは、その後も数年間(例:10年間)続く取り決めになっていることもあります。
このとき、会社として気になるのが「支払うときに源泉徴収(税金の天引き)が必要なのか?」という点です。
結論:通常は源泉徴収しなくてよいケースが多い
結論からいうと、これらの支払いが特許法でいう「相当の対価」に当たる場合は、源泉徴収の対象にならないのが一般的です。
会社が天引きする必要はありません。
「相当の対価」とは、従業員が持っていた「特許を受ける権利」を会社に引き継いでもらう見返りとして支払うお金のことです。
なぜ源泉徴収が不要になるのか
所得税のルールでは、特許権などの「使用料」を支払う場合、原則として源泉徴収が必要です。
「使用料」とは、他人が持っている権利を借りて使うために払うお金のことです。
しかし、職務発明の場合は少し違います。
特許法の考え方では、発明した従業員にはもともと「特許を受ける権利」があります。
ただし、会社が勤務規則や社内規程であらかじめ定めておけば、その権利を従業員から会社へ引き継ぐことができます。
そして、引き継ぎの見返りとして、従業員は「相当の対価」を受け取る権利を持ちます。
つまり、この支払いは次のような違いがあります。
- 使用料:権利を「借りて使う」ことへの対価
- 相当の対価:権利を「引き継ぐ」ことへの対価
職務発明への支払いは後者にあたるため、特許登録時の支払いも、販売実績に応じた継続的な支払いも、「権利を引き継いだことへの対価」と認められる限りは、通常は源泉徴収の対象になりません。
従業員側の所得の種類について
同じ「職務発明の対価」でも、支払い方によって所得の種類が変わることがあります。
一般的には次のように整理されます。
- 特許登録時に支払われる一定額 → 譲渡所得(権利を譲り渡した性格が強いため)
- 販売実績に応じて支払われる金額 → 雑所得(継続的・成果連動の性格があるため)
ただし、実際の契約内容や社内規程、支払いの実態によって判断が変わることがあります。
注意しておきたいポイント
同じように見える支払いでも、内容によっては「使用料」と判断され、源泉徴収が必要になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
- 会社が権利の引き継ぎを受けていないのに、従業員が持つ特許権を会社が使うために支払っている場合(実質的に「借りて使う」お金になる)
- 社内規程に基づく「相当の対価」ではなく、別途ライセンス契約(使用許諾契約)として支払っている場合
- 支払先が海外居住者である場合(源泉徴収のルールが異なる)
このあたりは、書類(社内規程、引き継ぎの手続き、契約書、支払基準)がきちんと整っているかどうかで判断が分かれやすいところです。
支払いの名目だけでなく、実態がどうなっているかが大切です。
安心して処理するために押さえておきたいこと
次の点を整えておくと、スムーズに判断できます。
- 職務発明の取扱い(引き継ぎの方法、対価の計算方法)が社内規程に明記されている
- 従業員から会社へ権利を引き継いだ事実が分かる書面・記録がある
- 支払いが「使用料」ではなく「相当の対価」であることを説明できる資料がある
「会社が特許を受ける権利を引き継ぎ、その対価として規程に基づき支払う」と整理できれば、源泉徴収が必要かどうかの判断がつきやすくなります。