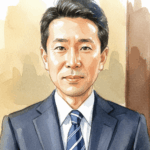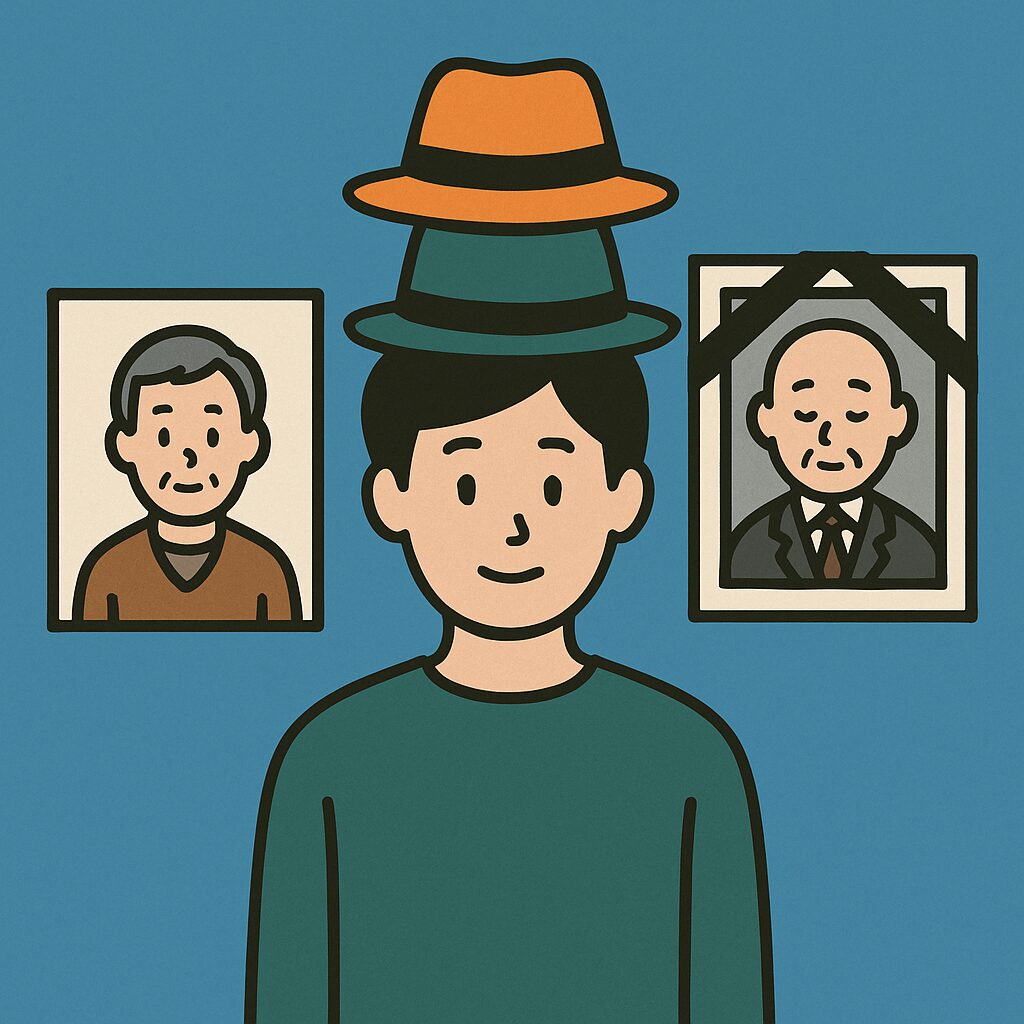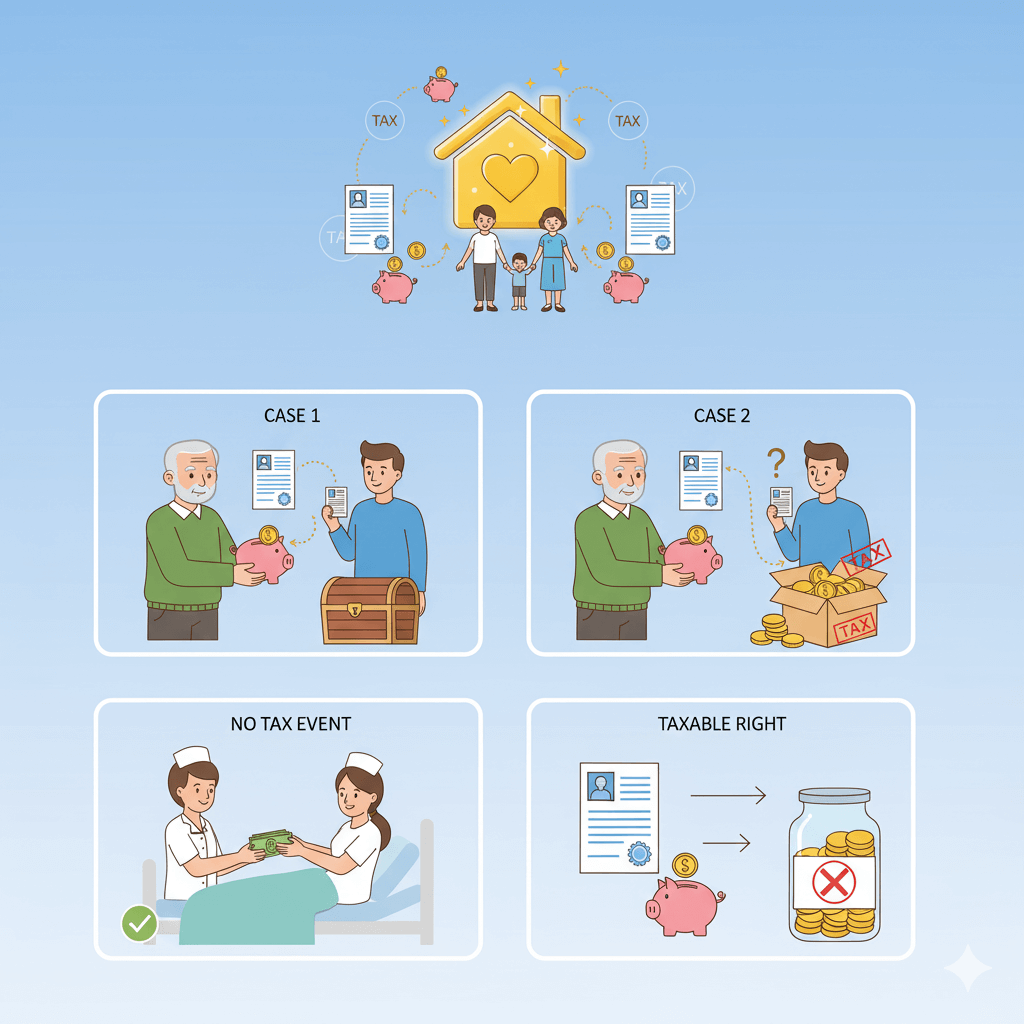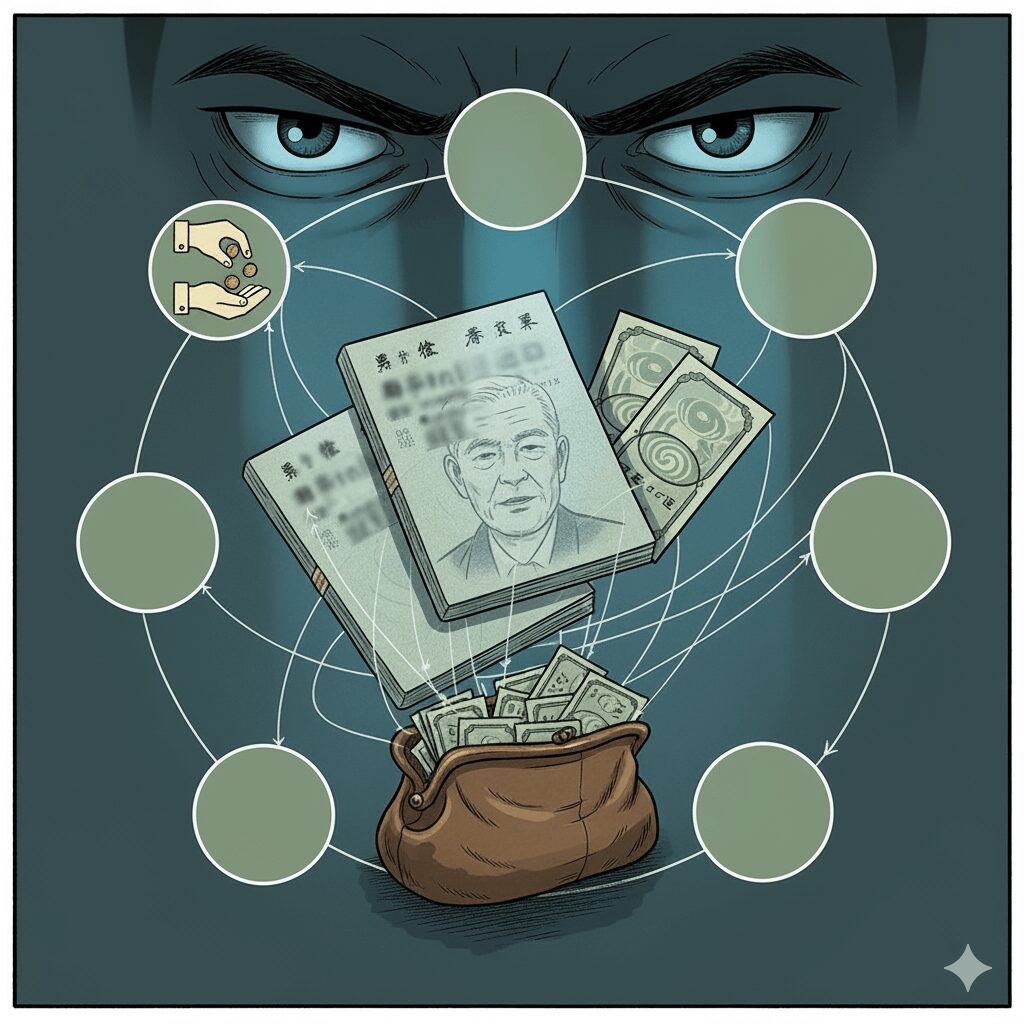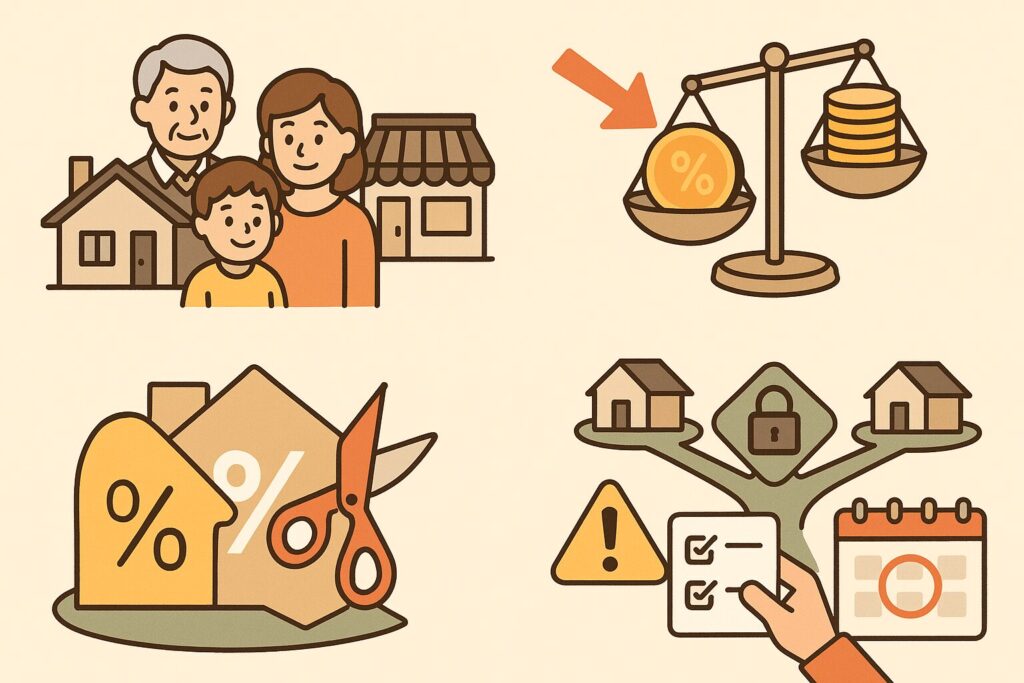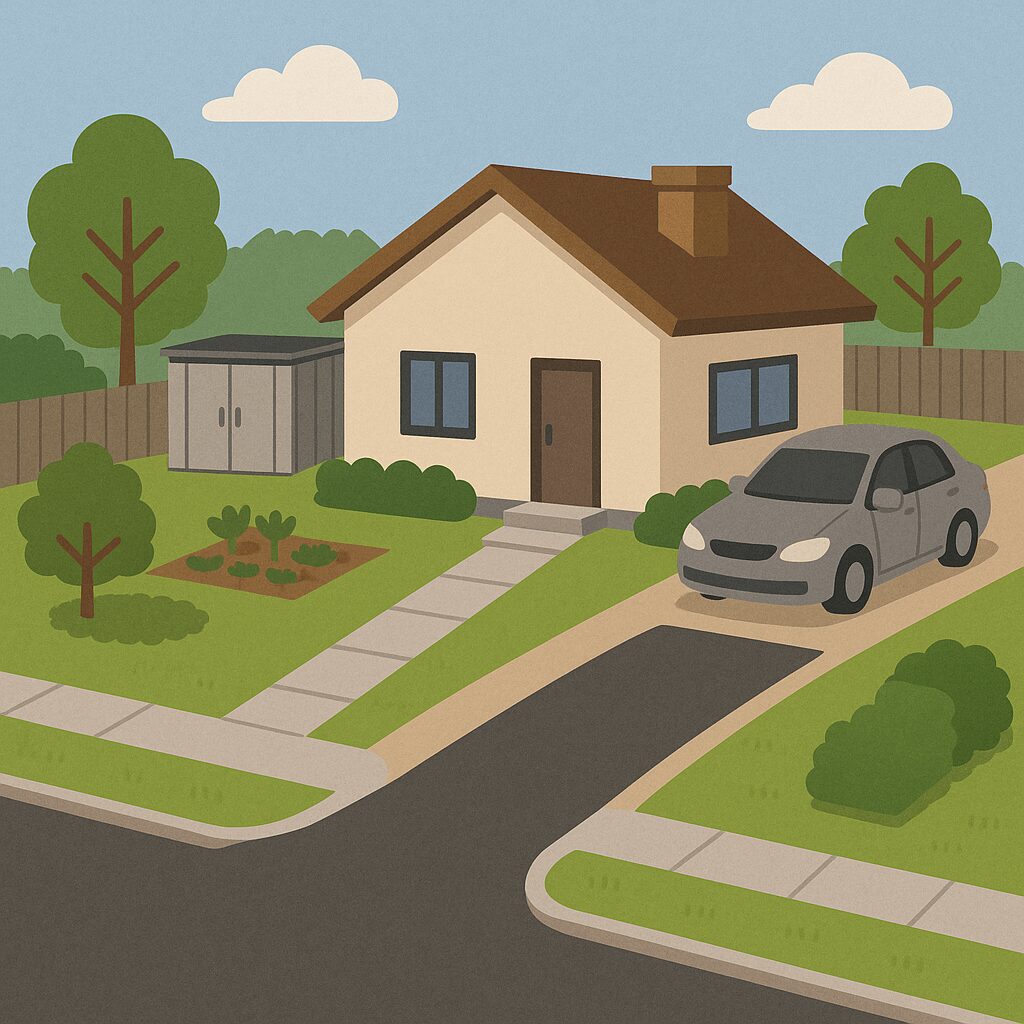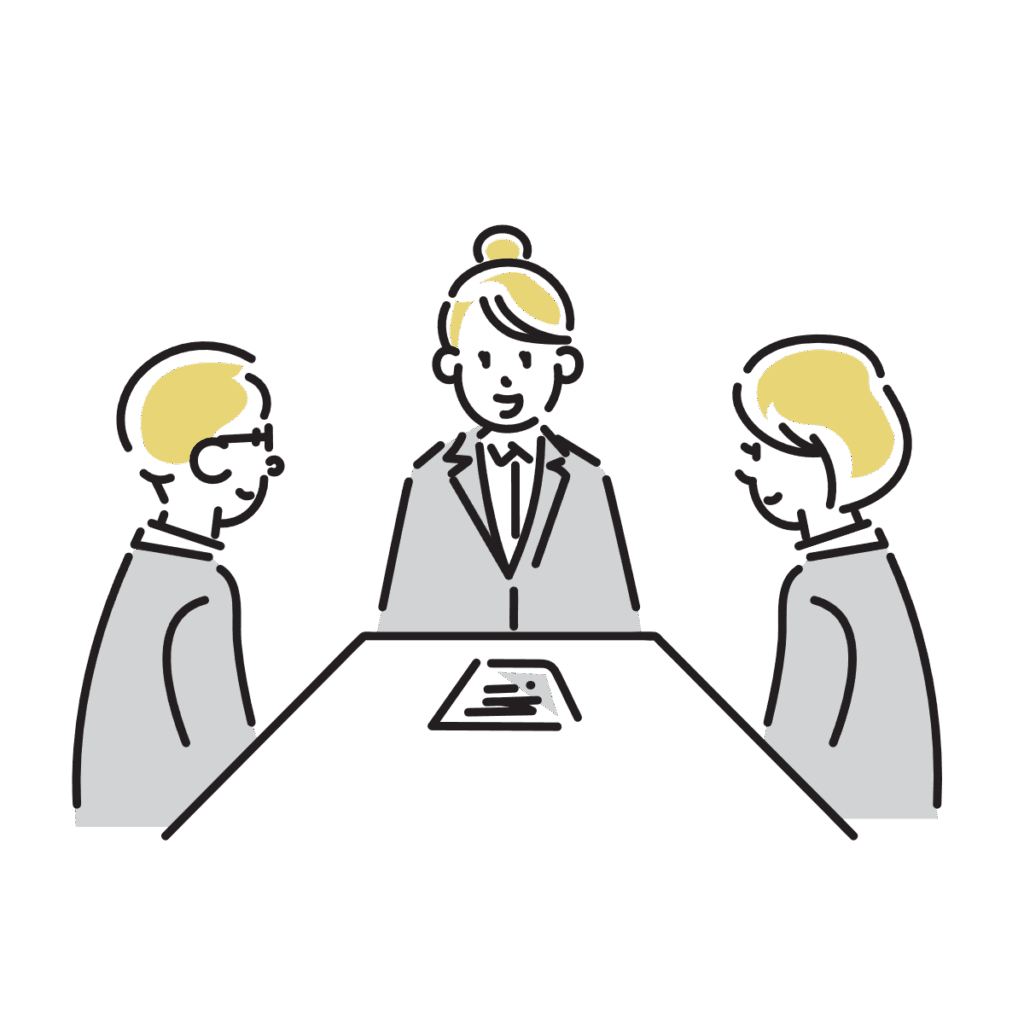
相続人の範囲と相続割合
【3つのケースで見てみよう!相続の割合はこう決まる】
相続で誰がどれくらい財産をもらえるか(これを法定相続分と言います)は、家族構成によって変わります。
まずは具体的な3つのケースで見ていきましょう!
ケース(1) 夫が亡くなり、妻と子ども2人が残された場合
相続する人: 奥さん(母A)、長男Bさん、次男Cさん
もらえる割合
- 奥さん(母A):半分 (1/2)
- 長男Bさん:4分の1 (1/4)
- 次男Cさん:4分の1 (1/4)
【やさしい解説】
これは最も一般的なケースですね。
まず、財産全体の半分を、人生のパートナーである奥さんが受け取ります。
そして、残った半分をお子さんたちで均等に分け合います。
まるで大きなホールケーキを、まず半分奥さんにあげて、残りの半分を子どもたちで仲良く分けるようなイメージです。
ケース(2) 子どものいない長男が亡くなり、妻と両親が残された場合
相続する人: 奥さん(妻Z)、お父さん(父X)、お母さん(母Y)
もらえる割合
- 奥さん(妻Z):3分の2 (2/3)
- お父さん(父X):6分の1 (1/6)
- お母さん(母Y):6分の1 (1/6)
【やさしい解説】
お子さんがいらっしゃらない場合、相続のメンバーが変わります。
この場合、一番に支え合ってきた奥さんの生活を守るため、3分の2と多めに財産を受け取ります。
そして残りの3分の1を、ご両親で半分ずつ分け合うことになります。
ケース(3) 子どもも両親もいない長男が亡くなり、妻と兄弟3人が残された場合
相続する人: 奥さん(妻E)、弟(次男F)、妹2人(長女G、次女H)
もらえる割合
- 奥さん(妻E):4分の3 (3/4)
- 弟(次男F):12分の1 (1/12)
- 妹(長女G):12分の1 (1/12)
- 妹(次女H):12分の1 (1/12)
【やさしい解説】
お子さんもご両親もすでにお亡くなりの場合は、奥さんと亡くなった方のご兄弟が相続人になります。
このケースでは、奥さんの貢献度や今後の生活への配慮がより大きくなり、財産の4分の3を受け取ります。
残りの4分の1を、ご兄弟で均等に分け合うというルールです。
【なぜそう決まるの?相続の基本ルールを知ろう!】
さて、なぜ上のような割合になるのでしょうか?
それには、法律で決められたいくつかの基本ルールがあるからです。
相続人には「優先順位」があるんです!
実は、誰が財産を相続できるかには、はっきりとした順番が決められています。
【いつでも相続人】配偶者(夫または妻)
奥さんや旦那さんは、他の誰がいるかに関わらず、常に相続人になります。
いわば「特別指定席」のようなものです。
【順番待ちの相続人】
- 第1順位:お子さん(もしお子さんが先に亡くなっていれば、お孫さん)
- 第2順位:ご両親(もしご両親が先に亡くなっていれば、おじいさん・おばあさん)
- 第3順位:ご兄弟姉妹
この順番がとても大切で、上の順位の人が一人でもいると、下の順位の人には相続の権利は回ってきません。
リレーのバトンのようなもので、第1走者(お子さん)がいる限り、第2走者(ご両親)にはバトンが渡らない、と考えると分かりやすいでしょう。
一番最初にすべきこと!「相続人は誰?」を確定させる
財産の分け方を決める話し合い(これを遺産分割協議といいます)は、相続人全員の参加が絶対条件です。
もし一人でも欠けていると、その話し合いは無効になってしまいます。
後から「実は知らなかった兄弟がいた!」なんてことになると、すべてがやり直しになり、大変なトラブルの原因になります。
そうならないために、まず最初に、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」を集めて、相続人が他にいないかを確認する作業が不可欠です。
少し手間はかかりますが、これはスムーズな相続手続きのための、最も重要な第一歩なのです。
【ワンポイントアドバイス】
- 「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある方を指します。
残念ながら、長年連れ添った内縁関係(事実婚)のパートナーには、原則として相続権がありません。 - お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)も、無事に生まれれば、相続人として数えられます。
- 養子縁組をしたお子さんも、実のお子さんと全く同じ権利を持ちます。
相続は、ご家庭の数だけ色々なケースがあります。