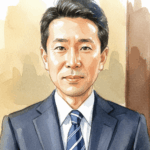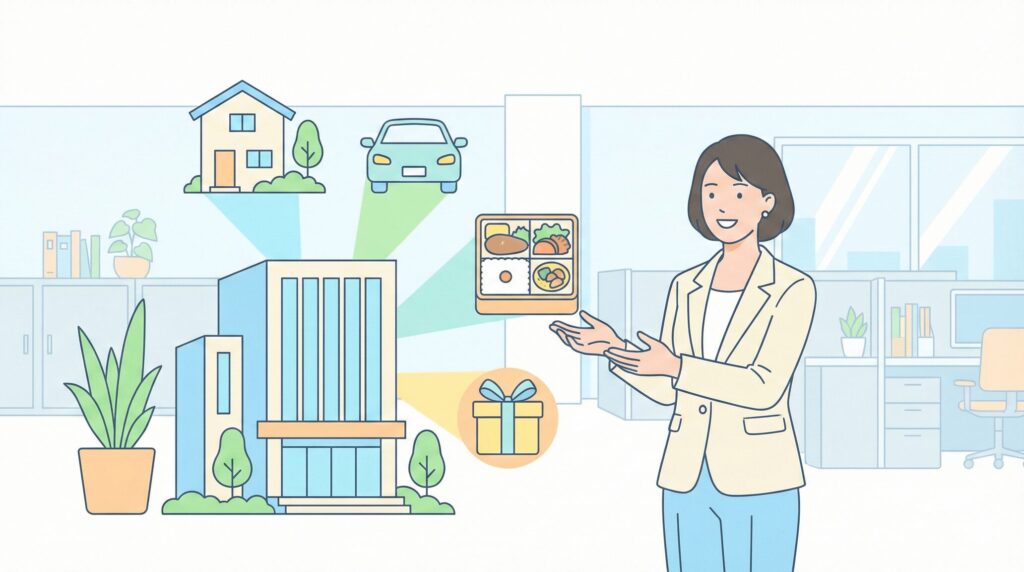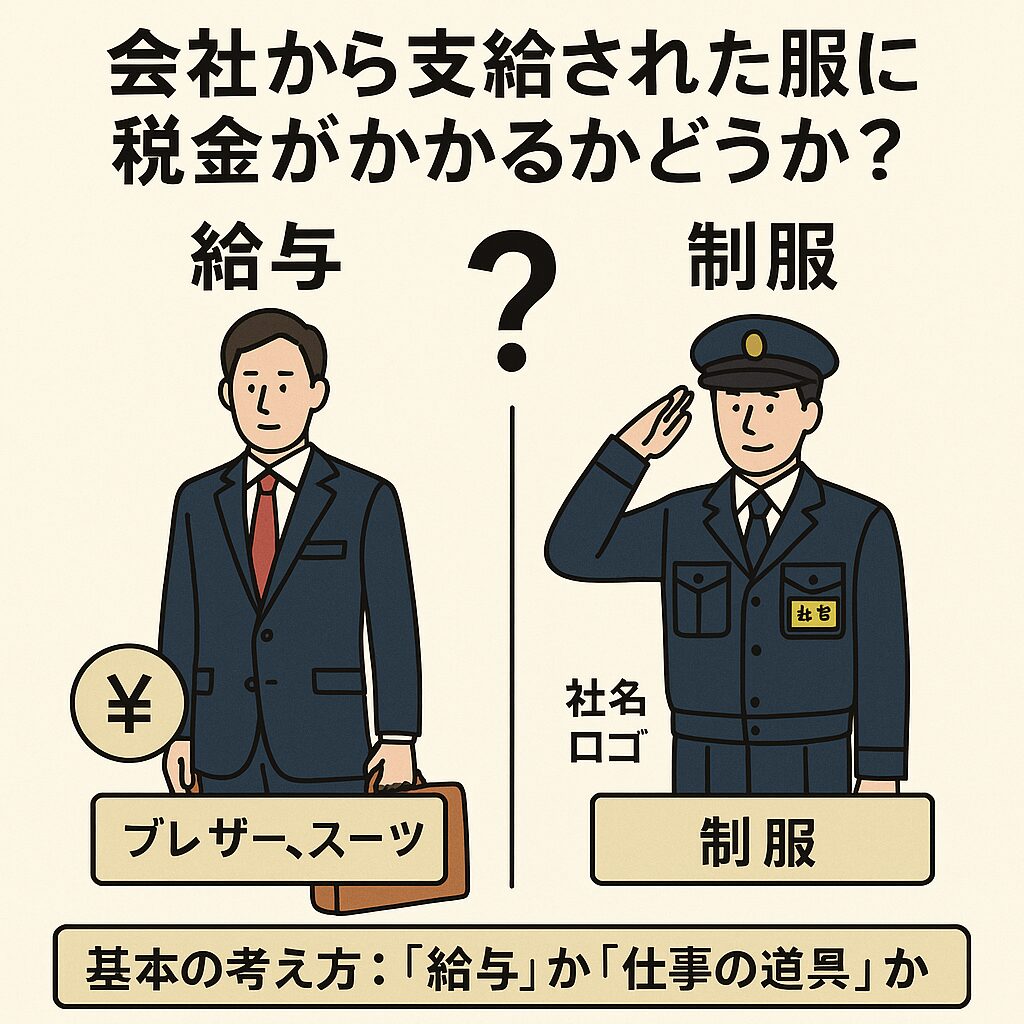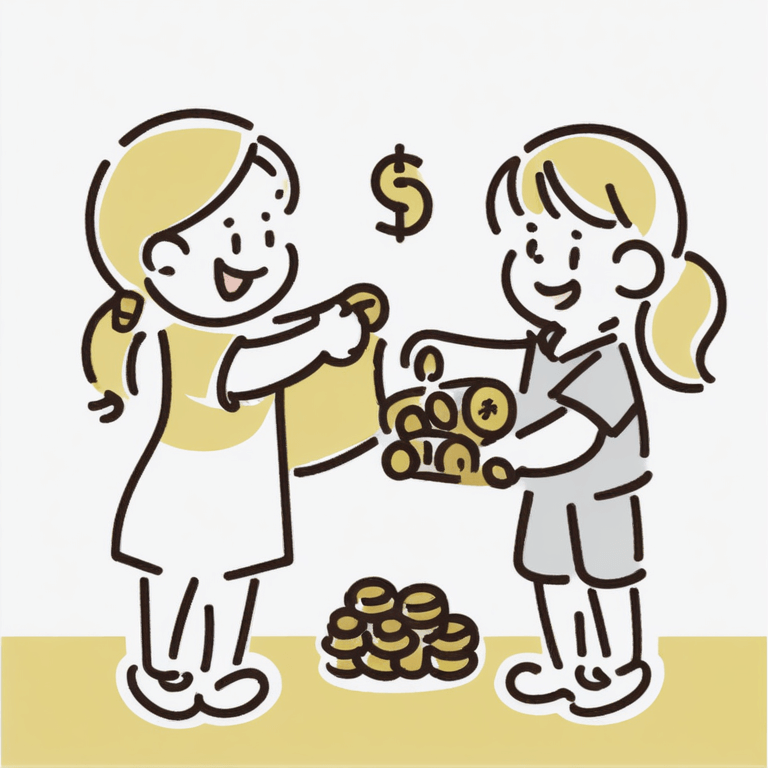
源泉所得税の端数計算
今回は、税金の計算で出てくる「細かいお金(端数)」の扱いについて、簡単にご説明します。
なんだか難しそうに聞こえますが、実は納税者にちょっと嬉しいルールになっているんです。
基本は「切り捨て」で、ちょっとお得!
確定申告などで最終的な税金を計算するとき、国は計算途中の細かい数字を「ないもの」として扱ってくれます。
これを「切り捨て」といいます。
お店で「端数はおまけしとくよ!」と言われるようなイメージですね。
これには、2つの大きなルールがあります。
税金を計算する「もと」の金額
税金の計算の土台となる金額(専門用語で課税標準といいます)に1,000円未満の端数があれば、それはバッサリ切り捨てます。
(例)計算のもとが「25万3,800円」なら、「800円」は切り捨てて「25万3,000円」として計算を進めます。
最終的に納める「税金」の額
いろいろ計算して、最終的に納める税額に100円未満の端数があれば、それも切り捨ててくれます。
(例)計算の結果、税額が「5万2,350円」なら、「50円」は切り捨てて、実際に納めるのは「5万2,300円」になります。
とっても親切なルールですよね。
【例外】毎月の給料から天引きされる税金は「1円単位」
「あれ?でも給料明細の税金は、もっと細かい金額だったような…」と気づいた方、素晴らしいです!
その通りなんです。
会社が給料から天引きする税金(これを源泉所得税といいます)は、いわば「税金の前払い」です。
毎月少しずつ税金を前払いしているので、この段階では1円単位まできっちり計算するのがルールです。
弁護士や税理士への報酬を支払う際の源泉所得税も同じです。
「前払い」の答え合わせの時に、切り捨てが復活!
では、いつ「切り捨て」の嬉しいルールが適用されるのでしょうか?
それは、1年間の「税金の前払い」を精算する「年末調整」や、「退職金」を受け取るときです。
- 年末調整: 1年間の給料に対する正しい税額を計算し直す「答え合わせ」の作業です。
この最終計算のときに、先ほどの「1,000円未満切り捨て」「100円未満切り捨て」のルールが使われます。 - 退職金: 長年勤め上げたご褒美である退職金についても、税金の計算ではこの切り捨てルールが適用されます。
ただし、年末調整の結果、もし前払いの税金が足りなくて追加で納めることになった場合は、その不足分は1円単位までしっかり計算します。