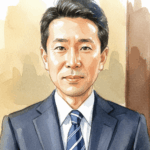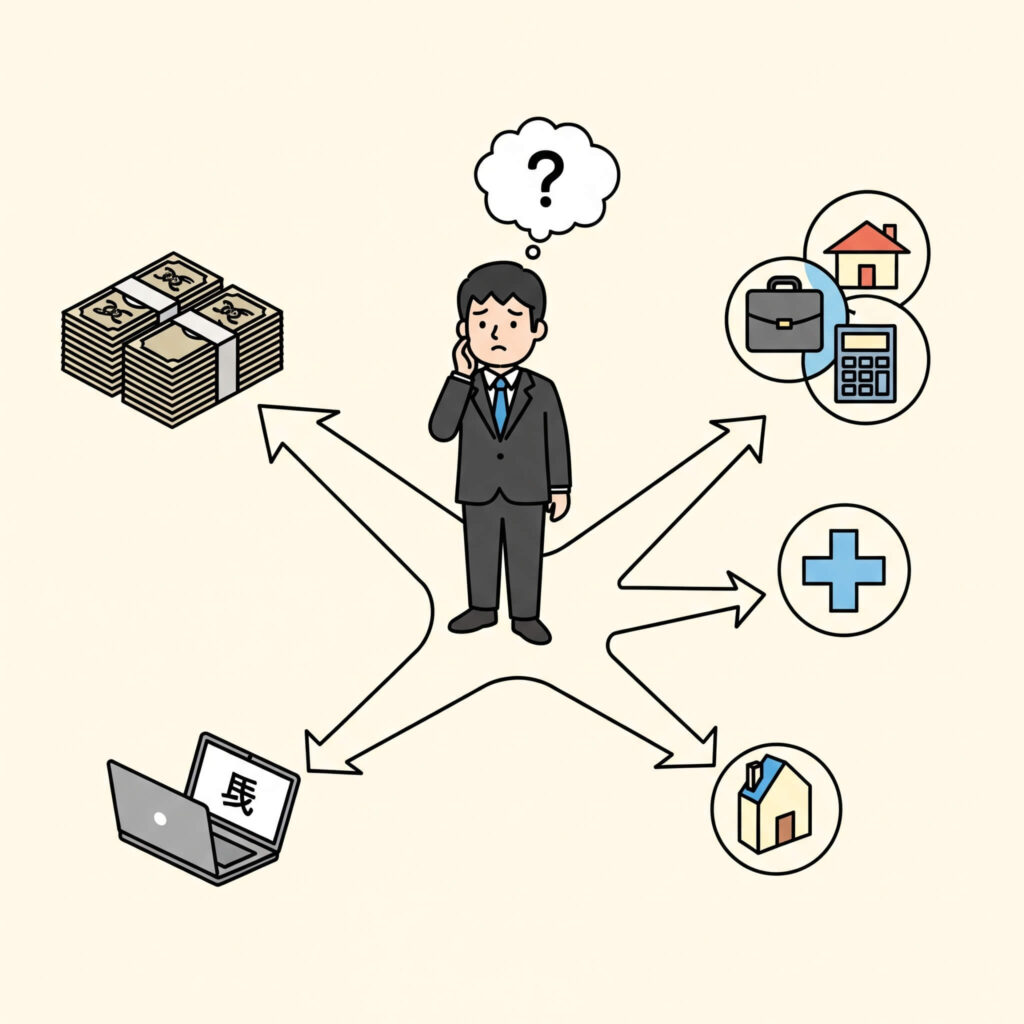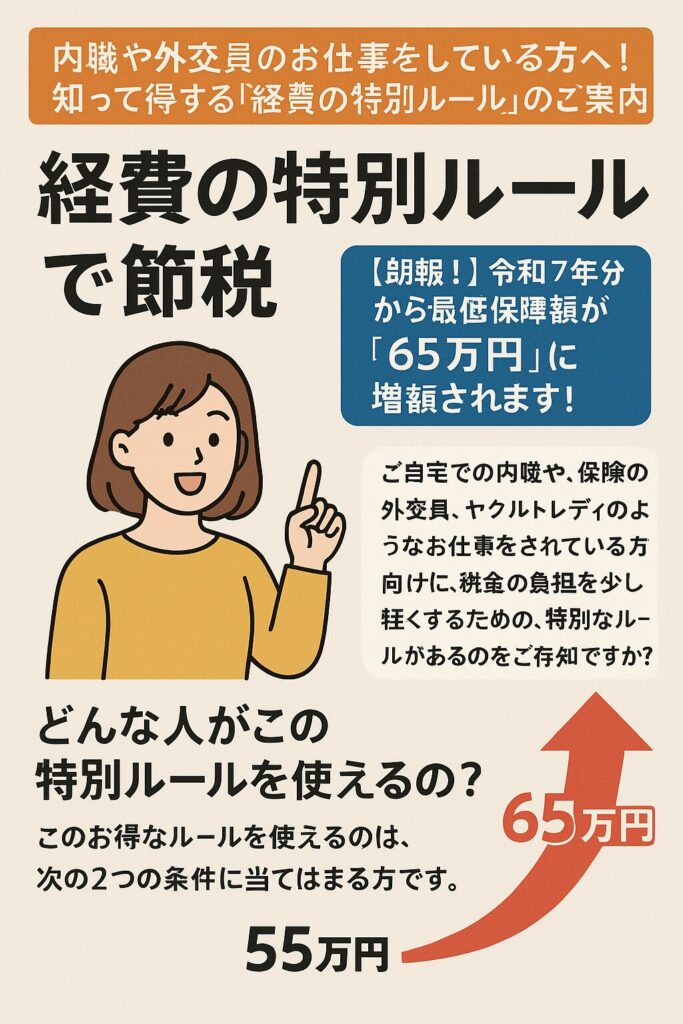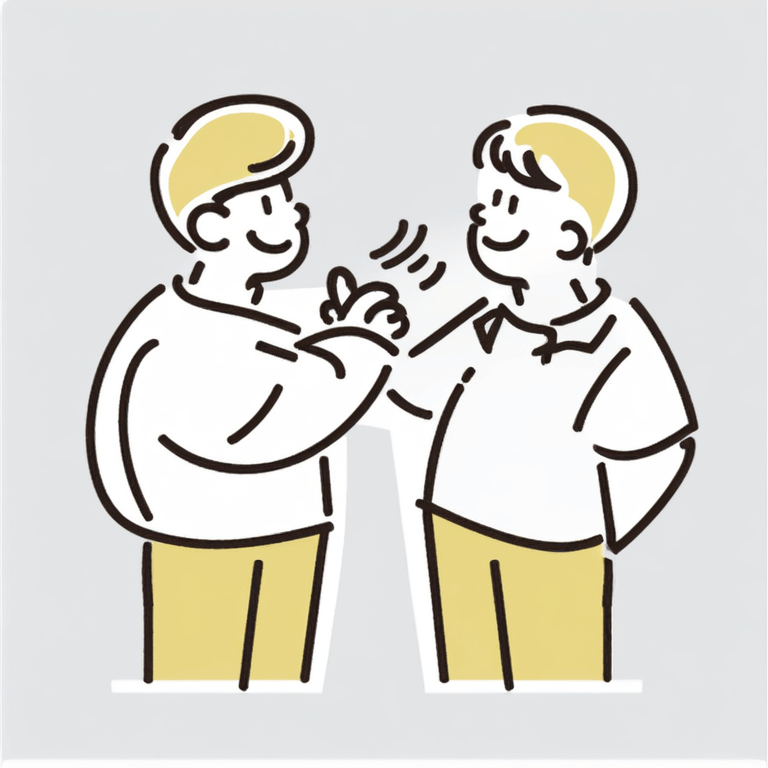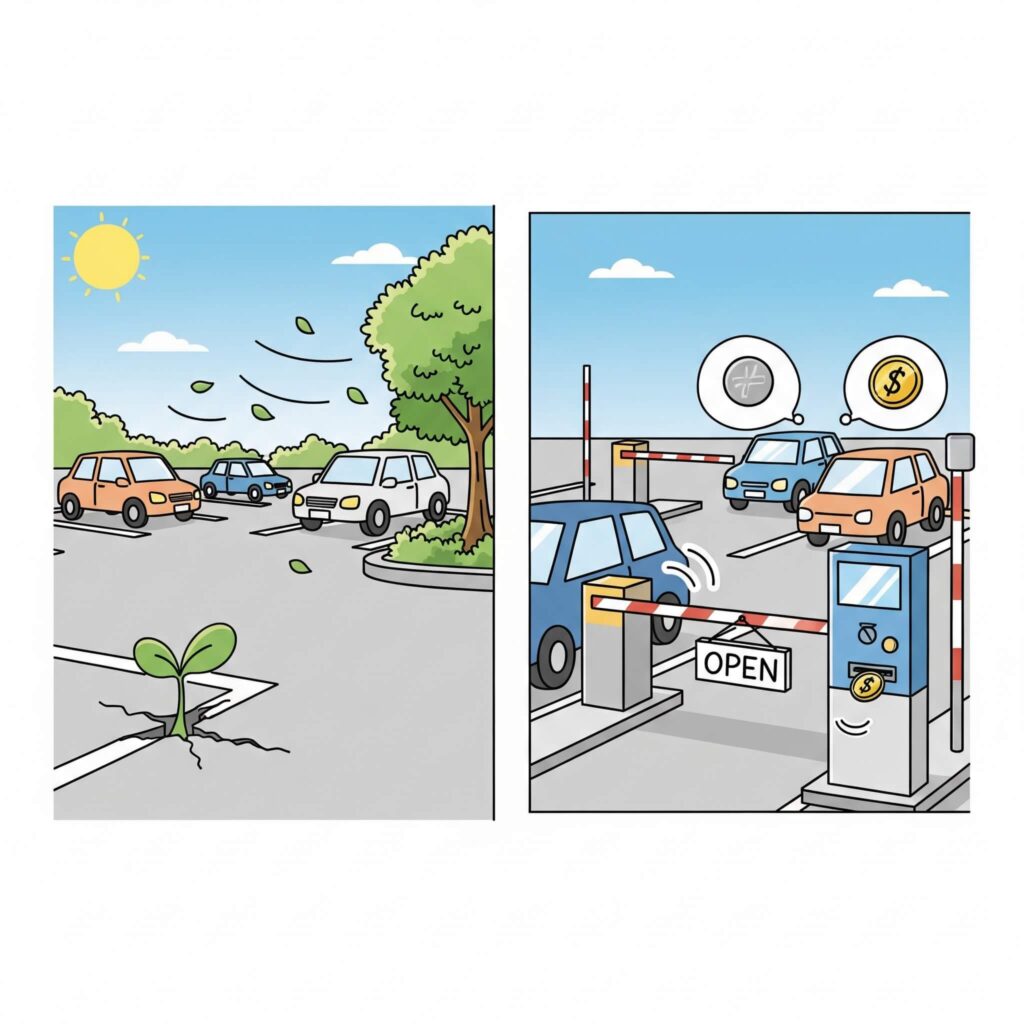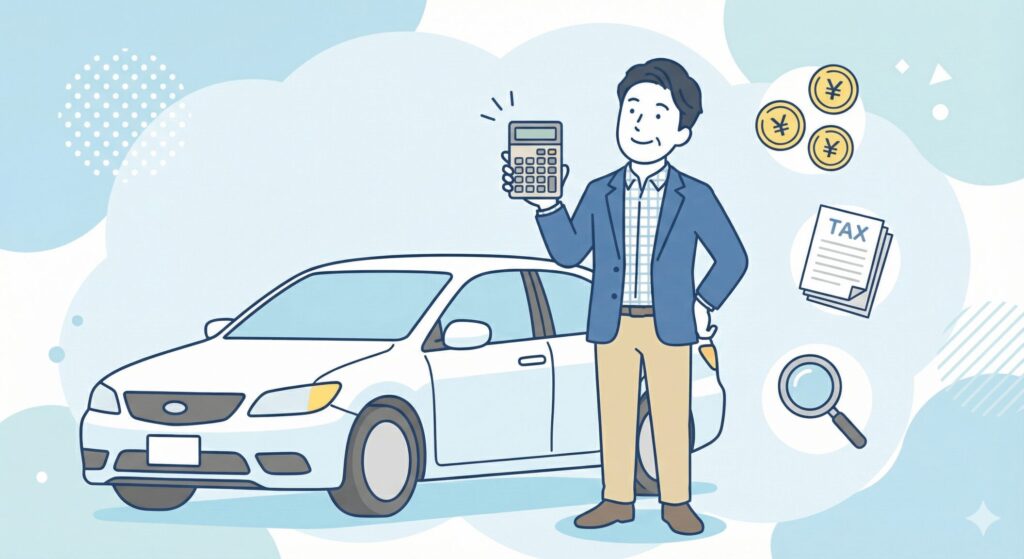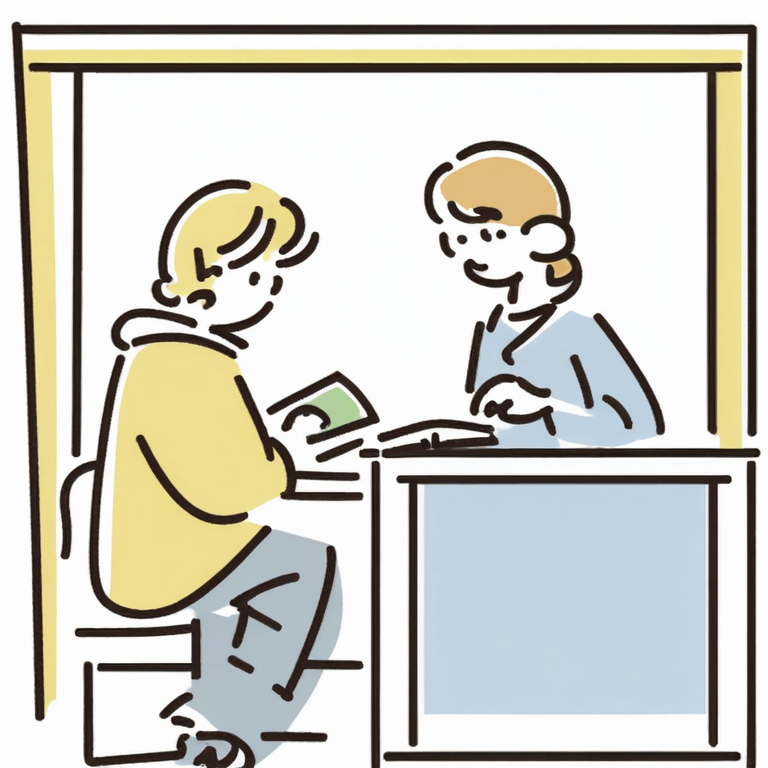
「住所」と「居所」、そして「納税地」、確かに分かりにくい言葉ですよね。
専門用語をできるだけ使わずに、身近な例でご説明しますね。
「住所」と「居所」の違いはなんですか?
一言でいうと、「生活の中心がどこか」で判断します。
住所
あなたの「メインの拠点(本拠地)」のことです。
例えば、ご家族と一緒に暮らしているご自宅や、お仕事の基盤があり、週末には帰って過ごす場所などをイメージしてください。
住民票がある場所と一致することが多いですが、必ずしもそうとは限りません。
「ここが私の生活の中心だ」と客観的に言える場所が「住所」になります。
居所
メインの拠点ではないけれど、ある程度の期間、継続して住んでいる「サブの拠点」のことです。
例えば、お仕事で1年間の長期出張を命じられ、その期間だけ借りている単身赴任先のアパートを想像してみてください。
ご家族が住むマイホーム(住所)は別にあるけれど、平日はずっとそのアパートで寝泊まりしていますよね。
このような一時的な滞在先が「居所」にあたります。
納税地はどう決まるの?【原則と特例】
所得税をどの税務署に納めるかという「納税地」のルールは、「原則」と、あなたの都合に合わせられる「特例(選択肢)」の2段階で考えるとスッキリします。
【原則】まずは「住所」で決まります
これが大原則です。
あなたの「メインの拠点(住所)」がある場所の税務署が、あなたの納税地になります。
【特例】あなたの都合に合わせて「納税地」を選べます!
あなたの生活や仕事の実態に合わせて、手続きに便利な場所を納税地に選ぶこともできるんですよ。
選択肢①:「居所」を納税地に選ぶケース
- どんなとき?
例えば、実家(住所)は地方にあるけれど、平日は都心の単身赴任先(居所)で生活しているような場合です。
仕事の資料も全部都心にあるし、税理士との打ち合わせも都心の方が便利ということもあるでしょう。 - どうするの?
確定申告書を書くときに、納税地の欄に居所地を書いて申告書を提出します。
選択肢②:お店や事務所を納税地に選ぶケース(主に個人事業主の方など)
- どんなとき?
例えば、自宅(住所)は郊外にあって、都心でお店(事業所)を経営している個人事業主の方を想像してみてください。
売上や経費の帳簿はすべてお店に置いてあり、税務署からの連絡や調査もお店に来てもらった方が話が早いですよね。 - どうするの?
確定申告書を書くときに、納税地の欄に「お店の場所」を書いて申告書を提出します。
まとめ
納税地のルールを整理すると、このようになります。
- 【大原則】 あなたの「住所」がある場所の税務署が納税地です。
- 【特例】あなたの都合に合わせて、
- 「居所(サブの拠点)」や
- 「事業所(お店や事務所)」を納税地に変更することも可能です。
なぜこのような選択肢があるかというと、税金に関する書類のやり取りや話し合いが、よりスムーズに進むように、という配慮からなんですね。