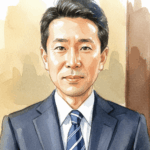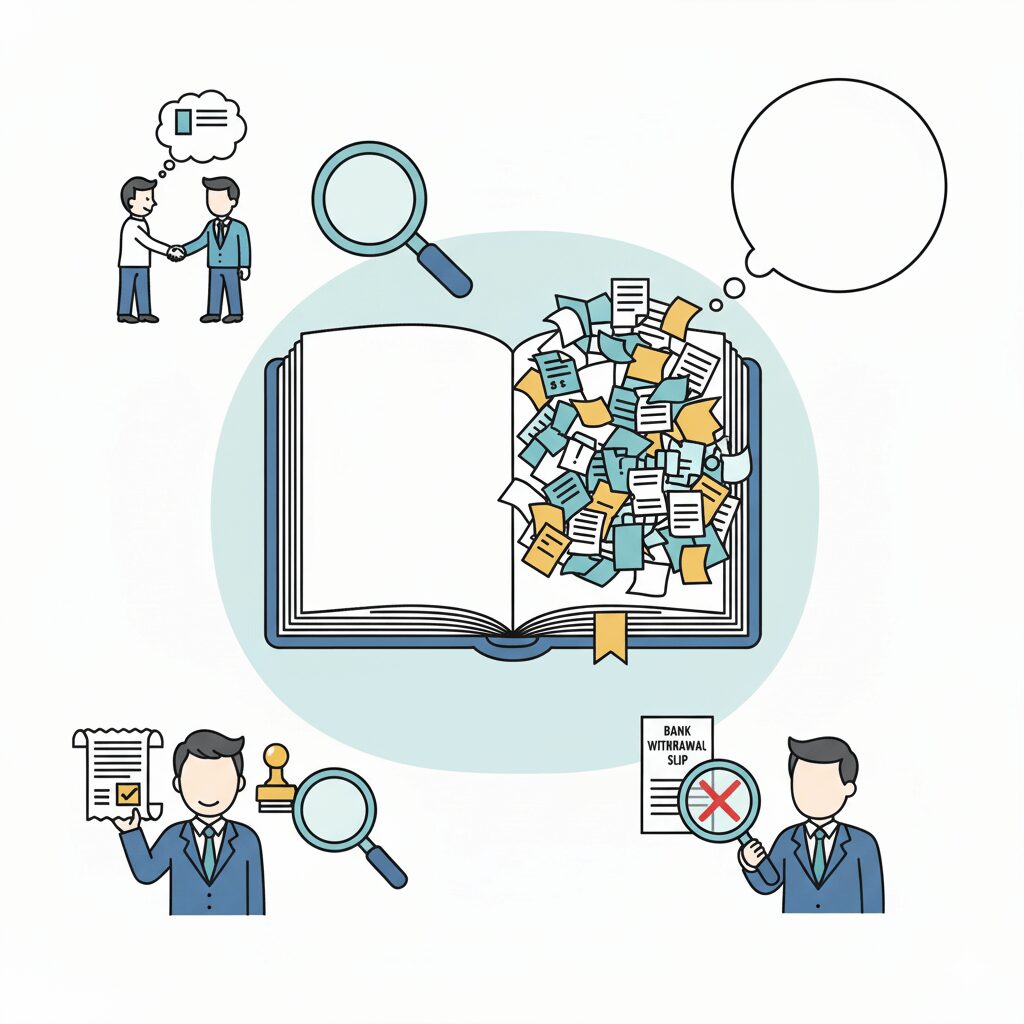
印紙税における課税文章の意義
そもそも「課税文書」って何?
一言でいうと、「国に税金を納めるために、収入印紙を貼らなければいけないと法律で決められた書類」のことです。
スーパーの買い物リストをイメージしてみてください。
国が「このリストに載っている書類を作ったら、印紙を貼って税金を納めてくださいね」というリスト(これを「課税物件表」と言います)を作っているんです。
このリストには、契約書や領収書など、全部で20種類あります。
なぜ判断が難しい時があるの?
この国のリストに載っている書類には、2つのタイプがあります。
- 誰が見ても分かりやすい書類
例えば、「約束手形」などです。
これは形がある程度決まっているので、「あ、リストに載っているあの書類だな」とすぐに分かります。
- 形が自由で分かりにくい書類
代表的なのが「契約書」です。
契約書は、作る人によってタイトルが「覚書」や「念書」だったり、内容も様々ですよね。
このように、書類の名前だけではリストに載っているものかどうかが判断しにくい場合があるんです。
これが、皆さんが迷ってしまう大きな原因ですね。
判断の決め手は「書類を作った目的」!
では、名前だけでは判断しにくい書類は、どうやって見分けるのでしょうか?
ここで一番大事になるのが、「その書類を、何のために作ったのか?」という目的です。
法律のリストに書かれているような「大切な約束事(これを課税事項と言います)を、当事者の間で証明する」という目的で作られた書類が、課税文書になります。
分かりやすい例でお話しします。
【例1:領収書】
お店が発行する5万円以上の領収書には、よく収入印紙が貼ってありますよね。
あれは、「お店がお客様から確かにお金を受け取りましたよ」という事実を証明する目的で作られているからです。
だから、課税文書になるんです。
【例2:銀行の払戻請求書】
一方で、私たちが銀行の窓口で「10万円引き出したいです」と書く「預金払戻請求書」には、印紙は貼りません。
- 私たちの目的: あくまで「銀行さん、私のお金を引き出してください」とお願いするためですよね。
- 結果として: 銀行にとっては「この人にお金を渡した」という証明になりますが、私たちがこの書類を作った本来の目的は、お金を受け取ったことの証明ではありません。
このように、「何のために作ったか」という本来の目的が「証明」ではないので、この書類は課税文書にはあたらない、というわけです。
「目的」は誰が判断するの?
「じゃあ、自分で『これは証明目的じゃないから』と思えばいいの?」というと、残念ながらそうではありません。
その書類のタイトルや内容を見て、社会の常識で「これは〇〇を証明するための書類だよね」と客観的に判断されることになります。
自分で勝手に決められるわけではない、という点がポイントです。
まとめ
課税文書かどうかを判断するには、
- 国のリスト(課税物件表)に載っている種類の書類か?
- 当事者間の大切な約束事を「証明する目的」で作られた書類か?
この2つのステップで考えます。特に契約書のような自由な形式の書類は、タイトルに惑わされず、その中身と目的で判断することがとても重要です。